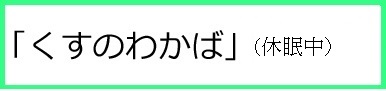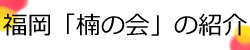
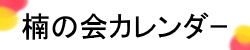
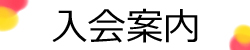
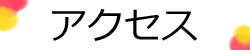
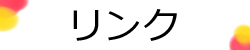
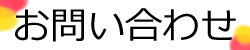
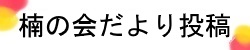
楠の会だよりNo.272号(2025年2月)記事より
霜 八木 重吉地は うつくしい気持ちを はりきって耐えていた
その気持ちを 草にも 花にも 吐けなかった
とうとう 肉を見せるように はげしい霜をだした
福岡「楠の会」作品展示会・
〔あすみんミュージアム〕にて開催中!
2025年2月1日(土)~2月15日(土)
冬に少し慣れてきた頃、節分と立春が続いてやってきます。
寒さに縮こまってしまいがちな日々、わずかな季節の移り変わりに目をやり、心を浮き立たせる行事を考えた昔の人の知恵に、”いいね”を発したいものです。
さて2月1日、会としても今年度最大のプログラム、福岡「楠の会」作品展示会をあすみんミュージアムの場をお借りして開催にこぎつけました。
社会を忌避し、自分に閉じこもる人たちに何かしら近づく方法はないものかと誰しもが考えています。
彼らはひきこもりながら生活していますが、何もしていないと言うわけではありません。
ゲームだけしているように見えてもやり方に工夫を凝らしているかもしれません。
或いは料理をしたり、散歩をしたり、行きつけの図書館やお店があったり、同じ生活をしてはいますが、親は知らないだけ、積み重ねた何かを持っていると言っても間違いではないと思います。
そんな彼らに、何か外へつながることはないかということで、彼らの創作品や、何かやっていること、形になるもの・ならないもの、或いは持ってこられない場合は写真で、などを一堂に集めて展示会をするプログラムを計画していました。
ちょうど「あすみん」では館内の壁面とその周辺にテーブルを置いて展示会をする「あすみんミュージアム」を募集していましたので、応募して今回この展示会の実現に至りました。
予想に反して当事者の出品物も集まり、所定の壁面も展示台もいっぱいになりました。親御様の趣味の制作物や、自分の思いを込めた「文字」も展示しています。この展示会出品に当たり、親子の会話ができたと言ういいお話もいくつかお聞きしました。
展示物の一つに、福岡「楠の会」の20年の歩みがわかるようなこれまでの会報、「くすのわかば」(若者向け会報)、第8回全国大会福岡大会の資料とその時の全国紙「旅だち」や著名な講師をお招きした講演会のチラシを収めたファイル、そして講演会のテープ起こしをした冊子数冊とひきこもり関係の参考図書を並べた本棚を置いています。
また2月11日(祝)午後2時より、福岡の集いとして、展示物を出品された当事者や他地区の家族の方とご一緒に交流会をいたしますので、ぜひご参加ください。
=========================
< 投稿Ⅰ >
『スピリチュアリティ』について
~NHKラジオテキスト「こころを読む」(石丸昌彦)再考
2月号上記投稿から一部分を抜き出して以下に掲載します。
さて、11月の会報は石丸昌彦先生のテキストに基づいた記事がありました。テキストを読んでみると、アメリカ在留時のエピソードがありました。長男の幼稚園入園時、園長先生の入園説明会でこれから4つの面でお子さんの成長が楽しみですよと言われました。その4つは1998年、WHOの健康の定義追加問題と全く重なるもので、成長の一つが「スピチュアルの成長」だったというのです。
〇スピリチュアルの成長とは
「スピチュアルの成長」とは何でしょうか、人生に意味を見出す力の成長でしょうか、或いは希望を持つ力や感謝する力の成長でしょうか。いずれにしても哲学的な或いは倫理的な面があるように思います。
関西学院大学で死生学を教えておられる藤井美和先生は2009年7月のEテレ「こころの時代」の中で次のように話されています。「スピリチュアルな痛みというのは、人間の存在の根源的な痛み、生きてていいのか、何故こんなに苦しいのかという痛みで、人間存在の意味は自分で見つけ出してこそ意味がある。人から答えを教えてもらうものではない。スピリチュアルケアというのは寄り添うことだ。ありのままを受け止めることだ。」と話されました。
自己実現の段階に達しておれば死を超越しているかも知れない。しかし多くの人は真の自己実現に達していないのではないか。もちろん私は達していない、自己実現の意味さえ分からない。
吉田兼好は「死を怖がるのなら、命を慈しめ。生きている間に命の尊さを感じず、死の直前で怖がるのは、命を大切にしていない証拠である。人が皆、軽薄に生きているのは、死が刻々と近づく事を忘れていると言っても過言ではない。」と徒然草で述べているように、多くの人は自分が死ぬ身であることを忘れて死に直面した時に絶望感に陥いり慌てふためくのではないでしょうか。
そんな時に寄り添って頂けるのが、スピリチュアルケアの実践者です。
=========================
今月は他にも素晴らしい投稿記事があります。ぜひ「楠の会だより」をご覧ください。
なお、当ホームページに「楠の会だより投稿」のサブページを設置しました。
こちらの方もご利用ください。
投稿の一部を掲載しています。→楠の会だより投稿
==========================
福岡「楠の会」支部会だより
数ある支部会だよりからいくつかの支部をWEB編集者独断で選んでいます。他の支部会の状況をご覧になりたい方は、「楠の会だより」をご利用ください。★筑紫野の集い 1月 8日 ( 水)14 : 30~16 : 30 ( 筑紫野市 生涯学習センター) 参加者7名 (女性 7)
運営委員より作品展示交流会の現在の作品応募状況等の報告がありました。筑紫野支部会からも数名の方々が出展される予定です。年末年始の子供達の様子を話しました。
〇 Aさんは年始に来た兄弟姉妹の配偶者と対話する当事者の事を話されました。
「いつもの当事者とは別人でした。仕事でもあのように明るい自分を演じているのだろうなと思いました。あれでは疲れるのも無理はないと思いました」。当事者の気苦労を垣間見る思いでした。
〇 Bさんの所は年末の掃除を手伝ってくれたそうです。会員の皆さんが年を重ねてこられているので、大助かりだったのが共感できます。
〇 Cさんの所は、兄弟姉妹の帰省に合わせて離れて暮らしている子供さんも帰って来られたそうで「たくさん食べて帰りました」と話されました。その一言を聞いてほっこりしました。元気な様子がうかがえました。子供と会って、話して、食事ができることはうれしいことです。
〇 Dさんは、12月に放送された日本テレビの「NNNドキュメント」(「3分クッキング」「笑点」に続く3番目の長寿番組だそうです)を見ました、と報告されました。その放送は、孤立した人達(45才のひきこもりと虐待されて育った高校生)に居場所を提供して、再出発を支える支援者「第2の家」の話でした。
〇 Eさんは、「離れて暮らしている子供の所に正月のお餅や料理を持って行ったので、子供の様子を知ることができた、ちゃんと一人暮らしができているようだが、帰宅するとまた色々心配な事(子供の部屋の掃除や整理整頓ができていない)がでてきて眠れない」と話されました。
〇 Fさんは、兄弟姉妹が来ると自分の部屋から出てこないお子さんの事を話されました。すると「どうして出てこないのか聞いてみましたか」と尋ねる方がいて、確かに私も当事者の行動を自分勝手に理解しているつもりになっているところがあるなと、反省しました。つい、またキツイ言葉の返事が返ってくることを恐れて、聞くことを避けてしまっているのでしょうね。(M・K)
★有明の集い 1月 11日 ( 土)13 : 00~15 : 00 ( ひとびと暖話室) 参加者4名 (男性1、女性3)
〇 今も昼夜逆転の生活を送っています。その中で先月、ある方の訪問を受け、一つのテーブルを囲みました。対話は出来なかったけど、質問に僅かに頷く瞬間がありました。有難かった。今後も少しずつでいいので、続けていきたいと思いました。〇 先々月の事です。仕事先でトラブルがあり退社。その後、部屋に閉じこもり状態となった。食事も別々。これからどうしていこうかと迷っている。
〇 最近本人の健康状態が気になる。清潔感の強いのもあるが、食事が偏ってきているようだ。父親との間が大きな溝。一緒に食事など全くない。本人が変わることより、まず自分が本人を受け入れる器になることを意識していこうとは思うが、なかなか難しいところである。少しずつ一緒に歩いていくしかないとは思っている。
等々、思いを語って頂く。解決しようと思うと、相手に変わってほしいと思う。その中で改めて、本人をどんな受け皿で受け止めるかが大切ではないかという思いも、少しずつ共有していこうと感じた例会であった。(G・M)
★久留米の集い 1月 24日( 金) 14 : 00~16 : 00 (えーる ピア久留米) 参加者 4名 ( 女性 4 )
〇 今日も参加者が少なかったです。「お店に野菜が少なくて大変」という話題から、地球温暖化を何とかしなくては、アメリカがトランプ大統領になってまたパリ協定から離脱すると言うのはどうなんだろうと、世界の話に広がりました。〇 先月号会報に出ていた四戸先生が紹介されたグラフには、戦後すぐは第一次産業である農業人口は人口の40%だったのが、2020年には3.3%にまで低下して、代わりに第3次産業サービス業が同じ年には73%に急上昇したと出ています。第2次産業である製造業も低下しているということですが、このことがひきこもりと関係があると言うお話です。コミュニケーションスキルを求められる職業が増えたことが、それを苦手とする人たちには、“社会に出て給与をもらうことが非常に難しい社会(世界)であることは明らかです”と言われます。
〇「私たち親が育った頃は、川で泳いで洗濯もして川がよく使われていたけれど、いつの間にか川が汚くなってたね」とか、「家業が農業で家の手伝いをして、親の働く姿をじかに見ていたけれど、子どもたちは会社勤めの親の働く姿を見ていない、それも影響したのかしら」「日本は食料自給率が40%だとか、耕作放棄地が増えているなかで、国は何の手も打たないで輸入に頼っているけど、もっと農業を大事にしなくてはいけないはず」とか話題が弾みました。そのほかには娘の方が親に厳しい、親亡き後の対策として、生協の名義を息子の名義に変えようかなどと話題が尽きず、時間いっぱい使いました。(K・M)
↑楠の会ホームページトップへ