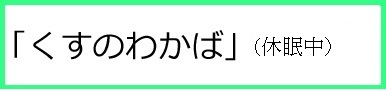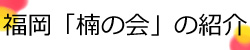
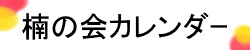
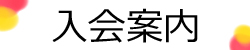
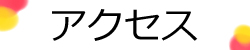
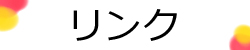
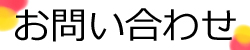
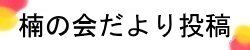
楠の会だよりNo.284号(2026年2月)記事より
春されば まづ咲くやどの 梅の花ひとり見つつや 春日暮らさむ
(山上憶良)
ひきこもりが長引くのはなぜ?
~「中高年ひきこもり」(斎藤環著)より考えてみよう~
このところ会報で取り上げてきた課題が、なぜひきこもりが日本に起こったのか、と、8050問題と言うように、なぜこうも長引いてしまうのかを考えてきました。特に長引くことについては、2月11日の富田伸先生の講演会を手始めに、今後支援者の皆さんと共に考えていきたい課題として、学習会などやっていく予定です。
ところで私たちの問題についてどこかにいい説明や見解などがないかと探していたところ、本当に偶然にごく手近なところで見つけました。それは、先月もご紹介した「中高年ひきこもり」(斎藤環著・幻冬舎新書)の中にありました。著者斎藤環先生は、思えばひきこもりの発見者でもあり、世に広め、その後もひきこもり問題に特化し、学者として支援者として、著書や講演会を通して私たちひきこもり問題に苦しむ者たちに、多大な貢献をしていただいて現在に至っている方です。
ひきこもりがなぜ長引くのか、それに該当する箇所を、少し長文になりますが、以下同著の<第7章成熟した社会の未成熟な大人たち>よりご紹介します。まずは最後までお読みください。
〇もし「絶対にひきこもらない手法」が発明されたらひきこもりという現象は当事者個人の資質だけで原因を語れるものではありません。むしろ私たちの社会がある種の必然として生んでいるものだと考えたほうが良いでしょう。
この20年の間に、そういう理解はそれなりに進んできたと思います。2000年の二つの事件(新潟女児監禁事件・佐賀バスジャック事件)で初めて世間の注目を浴びた時は、「働かずに親に養ってもらうのはけしからん」というバッシングばかりでしたが、今は同情論もかなりみられるようになってきました。特にネットの議論は、ひきこもりとの親和性が高いようです。少なくともひきこもりを擁護する声をあげることを躊躇する必要のない状態にはなりました。しかし雑誌やテレビなどのオールドメディア、或いはなんでも叩きたがる人達の集まるネットメディアのコメント欄などでは相変わらず「怠けているのはずるい」「親の育て方が悪い」「甘えを許すな」と言ったバッシングが優勢です。‥‥‥
しかしここで考えて見て欲しいことがあります。もしひきこもりが未然に防げたらそれは私たちの社会にとってよいことなのでしょうか。‥‥…例えば「絶対にひきこもりにならない手法」が発明されたとしましょう。小学生ぐらいのうちにそれをやっておけば、その人は死ぬまでひきこもらず常に何らかの形で社会参加を続けます。はたしてあなたはその手法をすべての子どもたちに適応すべきだと考えますか。ひきこもりをバッシングしている人たちは勿論、ひきこもりに同情的な考えを持っている人も、おそらく「イエス」と答えると思います。
〇ひきこもりは予防すべき「病気」だろうか
でも私は、ひきこもりを未然に防ぐべき、即ち予防すべきだとは考えません。何故なら、まずその発想はひきこもりをニュートラルな状態として見ていないからです。価値判断とは無縁のニュートラルな状態は、そもそも「予防」という発想とは無縁であるにもかかわらず、最初から病気、つまり「治すべきもの」と見ているわけです。
またひきこもりを予防する方法を子どもたちに適用するためには、まず「ひきこもりはよくない」「ひきこもりになったら人生おしまいだ」という価値観を植え付けなければいけません。予防接種を打つ時は、「この病気は怖い」という情報を与えなければ納得してもらえないのと同じです。
病気が怖いと言う価値観を植え付けることには、誰も反対しないでしょう。しかし「ひきこもりは予防すべき病気である」という価値観を社会全体が共有するのは、本当に良いことでしょうか。私は、それが社会全体にひどく悪い影響を与えると思います。ひきこもりが批判されるのは、彼らが「働かない」「納税しない」「親を苦しめている」などが主たる理由でしょう。しかし、生産性の有無で人の価値を判断すると言う発想は、きわめて危険です。
〇一億総活躍社会」ではなく・‥‥
そうやって世の中の大多数と違うものを「悪」として排除しようとする発想は、いわゆる優生思想に繋がりやすいものです。しかしこういう考え方をする人は、決して少なくありません。不登校を社会悪としてとらえ、全員を再登校させることが社会正義であるかのように喧伝するところもあります。今は文部科学省でさえ、「不登校は問題行動ではない」と言っているのに、それを無くすことが社会の浄化につながると考えているに違いありません。
「働きアリの法則」というのがあります。「働きアリの2割はよく働き、6割は普通に働き、2割は怠ける」という法則で、集団が行動を起こすときにほぼ必ずみられる現象とされています。私はこれを社会にも応用できると考えています。
社会は常に「無為で怠惰(に見える)二割」を必要としている。それが労働力のバックアップなのか、それとも別の意味があるのか、その点は今は不問とします。ただ私には、二割程度の不活発な人口を抱える社会のほうが健全に思えるのです。特に根拠はありません。あくまでも直感です。
いうまでもなく、ひきこもりはその二割に含まれます。そしてその二割は、無駄な二割などではなく、社会が円滑に活動を続けるうえで必要とされる二割なのではないでしょうか。「一億総活躍社会」みたいな恐ろしい標語よりも、「二割さぼっても回る社会」を目指すほうが、バランスとしてはいい気がします。
以下、次のような項目で報告は続きますが、このホームページでは項目のみの掲載に省略させていただきます。内容をお知りになりたい時は楠の会だより284号をご参照ください。
〇せめて「ひきこもっても大丈夫な社会」
〇ひきこもる事が恥ではなくなったら、長期間のひきこもりは激減する!
〇結論 ひきこもりが長引く大きな要因は「世間体」でした!
〇長引かないためにどうすればいいか
(文責 会報編集担当吉村)
=========================
<これからの福岡「楠の会」について>
さて、そろそろ年度末に近づきました。昨年アンケートを会員の皆様に書いていただきましたが、私たちがこれから何をしていけばいいか、そして本人たちにどんな支援が必要か、もう待ったなしに等しい支援や政策もあります。来年度に向けて会がどんなことをしていくか、今スタッフの間で検討課題として取り上げている課題を少しご紹介しますと、
1.親亡き後当事者が生きていける条件は何か。すべきことは何か、何ができるか、できることがあればやっていこう。一人暮らしができるか(食事・掃除・洗濯・買物等)。
2.親亡き後の住まい方はどうするか。
シェアハウス・グループホームについて情報収集。
3.金銭、身の回りの整理整頓ができるか。
金銭的に生きていけるか。遺産その他の整理と本人との話し合い、兄弟姉妹との話し合い。
4.支援者のつながりがあるか、支援者・団体の情報収集。
5.本人の回復に目向けてどういう社会資源と繋いでいくか(同じ仲間との交流など)。
以上ざっと挙げてみましたが、皆さんからのお声をぜひお聞かせください。
=========================
今月は他にも素晴らしい投稿記事があります。ぜひ「楠の会だより」をご覧ください。
なお、当ホームページに「楠の会だより投稿」のサブページを設置しました。
こちらの方もご利用ください。
投稿の一部を掲載しています。→楠の会だより投稿
==========================
福岡「楠の会」支部会だより
数ある支部会だよりからいくつかの支部をWEB編集者独断で選んでいます。他の支部会の状況をご覧になりたい方は、「楠の会だより」をご利用ください。★筑紫野の集い 1月14日 (水)13:30~15:30 (筑紫野市生涯学習センター) 参加者5名 (女性5 )
今回は年末年始の様子等、1か月間の報告をしました。〇年末年始は当人の兄弟姉妹が日帰りで来たり、甥っ子姪っ子には、お年玉をあげたりしている人もいました。他方、兄弟姉妹にあまり会いたくないと、家を留守にした当事者もいました。
〇Aさんは、本人が自分は発達障害だと言っている事、また親である自分達が本人をひきこもりに仕向けて行ったのではないかとも言われました。
〇Bさんは最近、法務局で遺言書をつくって預かってもらったことを話されました。その前に、色々あちこちに相談に行かれて、法務局にたどり着いたそうです。書き直しもできるそうで、収入印紙代の4000円くらいで済んだそうです。参考になるお話を具体的に聞くことができました。また、当人の精神の不調についても話され、精神障害は14才から出ているというある先生の話を紹介し、自分の子供もそうであったと言われました。私の子供もこの頃に転勤し、そこから引きこもってしまいました。
〇Aさん、Bさんは当人が大学を出る頃は就職氷河期で、思うところに就職できなかったと話されました。
〇Cさんは体調が悪く病院通いをされていたとのお話。それを聞いた他の皆さんからもあちこちと病院に行っている話が続き、誰もが自分の身体の不調を抱えている事が判明しました。(M.K)
★福岡東部の集い 1月18日 (日)13:30~16: 00(コミセン和白) 参加者 7名 (男性3、 女性4 )
〇東区で「hanasou」(※)という地域カフェを会報でご紹介したことがありました。このカフェの存在を知らせて下さったAさんが、二人の支援者を伴って1年ぶりに来られました。このお二人もそれぞれ引きこもりや発達障がいの当事者を持つご家族だと言うことでした。Aさんはご自分でも傾聴ボランテイアや自治会活動をやっておられ、地域にひきこもりを抱えた世帯が多く存在しているとお話し下さいました。〇Bさんは来られるときは当事者の息子さんとご一緒に参加されますがこの前よりもお元気になられたようにお見受けしました。初めて来られた方のために小学生の頃からのひきこもり経験をお話しになりました。今彼は運よくバイオリンを手に入れて、独学で少し演奏ができるようになられたとのこと。スマホに録音している曲を皆で聞きました。
〇Cさんは親の自分が発達障がいだと思う、苦手な教科があって困ったけれど音楽は好きだったとにこやかにお話しされました。
〇何時も見える方が見えなかったのは寂しかったけれど、新しい方の参加のお蔭でとても有意義な楽しい集いになりました。(S・Y)
★久留米の集い 1月23日 (金)14:00~16:00(えーるピア久留米) 参加者3名 (女性3 )
〇寒い一日でした。それでも3名の参加。話し出すといつの間にか暖房もつけるのを忘れて一時間半もたっていました。ここにいるみんなが70代になり、病院通いや寒さがこたえるのか集まりが悪くなっています。新しい人が来ることも減り、今や古株に支えられています。〇今回ちょっと新鮮ないい話題をお聞きしました。佐賀市であった先日の斎藤環先生の講演会に参加されたSさんの話です。その日会場の参加者を6人ぐらいのグループ分けをして、さらに3人(A)と3人(B)に分け、〖自律と自立の違い〗について、まずAグループが自由に話し、その間Bグループは黙って聞いている。その後Bグループの人が聞いたことを基に話をすると言う方法。思ったことを気軽に話していいんだそうです。つまらないことでも、頭に思い浮かんだことを口にする、そうやって交代で話していく。
〇これをひきこもっている人たちを対象にやったあと、その人たちが気持ちが楽になったと言う感想があったそうです。こんなこと言ったら笑われるんじゃないかとか、恥ずかしい事かもとか自分の憶測を止めて、口に出しても誰からもそのことに関してとやかく言われない、非難をされない、安心感を作り出すことがこの場合大事なのかもしれないと言う感想でした。Sさんもその後気持ちが楽になって、息子さんに対しての声掛けが増えたそうです。(H・S)
↑楠の会ホームページトップへ