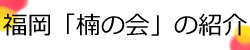
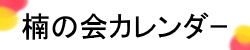
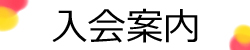
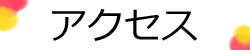
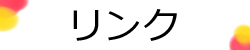
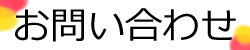
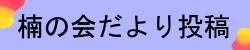
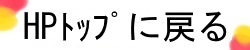
■楠の会だより投稿文の紹介■
< 投稿> 〔人生の壁〕(養老猛司著・新潮文庫)を読んで愛読してきた養老孟司氏の著作である「壁シリーズ」の最後かなと思われるのが、昨年10月発刊された「人生の壁」です。これは彼にしてはいつものような厳しい口調でなく、穏やかに読みやすく書かれています。その中で私が注目したのは、何度も取り上げてきましたが、なぜ日本に「ひきこもり問題」が浮上したのかという長年の疑問にひとつの回答を見つけた気がしました。
1945年の日本の敗戦を知っている最後の世代である養老先生の世代だから言えることですが、今まで日本国を形作っていた価値観、人生観、世界観が、戦争を引き起こした原因としてすべて廃棄しなくてはいけなかった「一億総ざんげ」。お寺も神社も家族制度も教育制度も地域の民芸や風習も、捨てる人が進歩派だと言われ、目はもっぱらアメリカ・ヨーロッパに向けられました。私もその一人でした。
養老先生の人々への警鐘は、戦後の大きな風であり今でも吹き荒れている風、都市化と個の尊重、それが行き過ぎていないかと言うこと。夏目漱石も問題視していたと言います。それに加えて地域社会のつながりの崩壊、そして先月の会報で四戸先生が指摘されたように、職業も第一次産業や職人的な職種が消え、会社組織が圧倒的に増えたということ、コミュニケーションが欠かせない職種になったこと、これらがひきこもり問題の根底にあるだろうということ、私自身、やっと腑に落ちたように思います。
養老先生が心配されるもう一つは子どものことです。意識第一で脳社会の産物であるコンクリートジャングルで育つ子どもたち。花鳥風月に触れず人工物に囲まれ、人の目を気にして自身の身体は自然物であることを考えてない、そんな社会で育つとどうなるか、心配はもっともです。今8050問題の渦中にあって思うことは、一応経済成長期の中で成功者である親たちが年を取って力を失っていくことは子たちにとって、自信を回復するチャンスかもしれないということです。
ただひきこもりに多い発達障がいと言われる特殊性の強い人たちへの支援の方策が、通り一遍な気がします。地球環境問題や人口減少問題のただ中、彼らの特殊性を活かすような社会参加を皆で考えていきたいものです。養老先生の「人生の壁」は示唆に富んでいます。ぜひご一読を!(Y・F)
