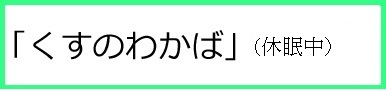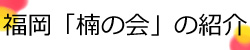
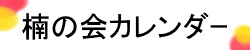
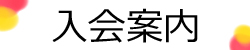
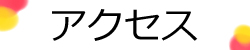
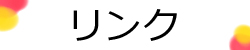
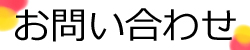
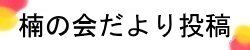
楠の会だよりNo.277号(2025年7月)記事より
夏は来ぬ (佐々木信綱作詞 小山作之助作曲)卯の花の匂う垣根に 時鳥(ほととぎす)早も来鳴きて
忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ
福岡「楠の会」アンケートにご協力お願い
ちょうどその日は久留米のえーるピアにいました。外に出ると真っ青な青空。気象庁からいきなり梅雨が明けたと発表があった日でした。今年の夏は水不足が心配ですね。
さて、新年度が始まって、会の集いにどれくらい会員の皆様が参加しておられるかを見てきましたが、やはり往年の頃とは様子がまったく違ってきました。どこの集いも参加者が少なく固定化している傾向にあります。それは必ずしも悪い傾向ではないかもしれないと言えるのです。これまでに退会された方々の退会の理由が、長い時間の経過の中で親がひきこもりについて学ぶうちに、子どもとの関係性が良くなり、それが子の社会性の復活を促して、ひきこもり状態からは抜け出して一般の社会人と同じ就労をしている、また福祉制度を利用して生活を整え、仲間もあり、親亡き後もなんとかやれるだろうと安心感の持てる状態になったなどという方々でした。
ただ会の集いの参加者の人数が減り、また固定化していること、新しい人が参加してもなかなかリピートしないという傾向にあるように思います。それは会そのものが二十数年の制度疲労に陥っていると言えるかもしれません。今の会に何か新陳代謝が必要になっている時期と考えていいと思います。
それでなくても今世界も日本も従来の価値観が大きく揺らいでいる時です。その渦中にあって私たちはもっと知らなくてはならないことがあるように思います。その上で智慧と行動力を以て私たちの願望が少しでも叶えられるようにやっていく必要があるのではないでしょうか。
特によく言われる高齢化はこの会でも顕著な傾向で、会場まで足を運べない方が目立ってきました。以前はよくお顔を拝見し、状況もお互いによくわかっていた方々が、今どうしておられるのか、どのようなことを考えておられるのか全く分からなくなりました。電話も掛けにくくなってきています。
こんな状況だからこそ聞こえない声を聞いてみる、そこで考えたのがアンケートという方法でした。
〇どんな生き方がいいか、夢物語でも‥‥
同封していますアンケートの内容をご確認いただきたいのですが、これは専門家を入れず、私たちスタッフの間で作成しました。皆様には多少のお時間を頂くことが心苦しいのですが、お暇な時間にボチボチこれまでの経過を振り返りながら書き込んでいただきたいと思います。振り返りは様々な心理療法で取り上げられています。特に日頃の雑事に追われて我が家の問題について整理して考える暇がない方には、問題点を見直すいい機会になるのではないでしょうか。
その他、日頃の思い、今後の日本社会でひきこもり型の人たちはどんな生き方ができるか、社会参加の場などのアイデアも歓迎します。そのほか詳しく書きたいことがありましたら、別紙又はアンケートの裏面をお使いください。以上のようなことがアンケート実施の趣旨になります。いささかなりともご賛同いただけましたら、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。なお返信は同封の封筒をお使い下さって、8月末までにご返送をお願いいたします。(会報編集部)
福岡「楠の会」では上記のように全会員向けにアンケートを実施しています。
=========================
<投稿 【オープンダイアローグ】を拝読して:感想>
臨床心理士T・M
いつも会報をお送りいただきありがとうございます。毎回、手記やテーマの文章を拝読しながら、お一人お一人の思いや体験に想像を巡らせております。前回のオープンダイアローグに関しても、大変興味深く拝読させていただきました。
『対話』は、今日さまざまな領域で取り入れられてきています。教育、医療、産業…そして近年、刑務所で加害者(受刑者)の矯正プログラムとしてオープンダイアローグの文化が導入されたことは、それまでの組織風土を大きく転換するものでした。おたよりの文面にありましたように、斎藤環先生がいち早くその効果に注目し、書籍などを通して多数報告されています。
残念ながら、今の日本の医療構造においてオープンダイアローグを「まるごと」導入することは困難ですが、その主たる実践である『対話』は、さまざまな病院のチーム医療で導入されつつあります。
「お医者様は神様だ」ではなく、医師もチームの一員であり、他の医療職も患者さんも同じくそのチームの一員であるという考え方は、対等に思いや考えを率直に伝え合える為、予後にもよい影響があるそうです。上下関係ではなくフラットな関係性で、且つ「その場」で率直な意見交換を行うことは、情報共有も円滑で、「誰かが聞いていなかった、知らなかった」「委縮して言えなかった」という事態も起こりにくく、医療ミスの軽減にも貢献するのではないでしょうか。当事者の思いや意見を聞き、そして支援者側も思いや考えを伝え合うこと、かならずしも全てが当事者の希望通りにいくとは限りませんが、「伝えられた」「聴いてもらえた」という感覚は、信頼関係もより強くするはずです。
このオープンダイアローグにみる対話構造は、かつてより自助グループで実践されてきたコミュニケーションの形にも通じています。「今ここ」で対等に思いを伝え合うことで、「自分一人ではないのだ」と孤立感が軽減します。それは、対等な繋がりからこそ生まれる効果なのではないでしょうか。
誰しも人は孤独かもしれませんが、孤立は避けなければなりません。「楠の会」は、対等に率直に話し合える場という、まさに対話実践の塲であり、オープンダイアローグの要素をいち早く取り入れ実践されている素晴らしい場所ですね。新たに来る人にも常に扉が開かれ、その文化と関係性が長く続いていくことこそ、回復に繋がる塲であると思っています。
=========================
今月は他にも素晴らしい投稿記事があります。ぜひ「楠の会だより」をご覧ください。
なお、当ホームページに「楠の会だより投稿」のサブページを設置しました。
こちらの方もご利用ください。
投稿の一部を掲載しています。→楠の会だより投稿
==========================
福岡「楠の会」支部会だより
数ある支部会だよりからいくつかの支部をWEB編集者独断で選んでいます。他の支部会の状況をご覧になりたい方は、「楠の会だより」をご利用ください。★宗像の集い 6月 18日(水) 13 : 30~16 : 00 (メイトム宗像) 参加者 6名 (女性5 、男性1 )
1 令和7年4月港区発達支援講演会より「学校の中の発達障がい」を視聴した。約30分
( 本田 秀夫 氏 / 信州大学医学部教授 )
医学の世界では発達障がいという言葉はあまり使われなくなって神経発達症という言葉になってきています。知的障がいは、発達障がいの中の一区分ですが、法律制定時の状況から日本の法律では知的障がいと発達障がいは別の法律になっています。小学校・中学校年代の子どもさんの約13パーセントが発達障がい者として特別な配慮を要する人がいると考えられます。うち6.3パーセントは特別支援学校、特別支援学級などで学び、一般のお子さんとは別の指導を受けています。残りの6.7パーセントの人は通常の学級に在籍しています。IQが高いから、或いは授業についていけるからと通常学級に通わせたい親御さんもいらっしゃいますが、そういった方たちのすべてではないですが、大人になってひきこもりに移行するリスクも残っています。発達障がいの人は興味の範囲が通常の人と重ならないことが多くて、みんなと行動をあわせようとすると過剰適応の状態になって、家に帰ってくるとぐったりするなどの状態になることがあります。このような状態からひきこもりに移行することもあるわけです。したがってこの年代の人が学校のなかでどう過ごすかが大きな課題になってきています。
2 みんなの声
a :うちの子どもは学校から帰ってきたときにはぐったりしていたのを思い出しました。過剰適応の状態だったのかも知れません。親や先生たちに発達障がいの知識があれば違った対応があったかも知れないが、当時の状況からやむを得なかった。
b :我が家の子どもはチック症状があったので、発達障がいの疑いがあると思う。
c :私が疲れて帰ってぐったりしていたら、娘がご飯を作ってあげるといってくれました。普段は週に1回作ってくれますが、疲れた私を見かねてもう1回作ってあげるといってくれ、ありがたかったです。
d : 娘は人と話そうとしても言葉が出てこないので、どうしたら良いか私にも聞いてきますが、良い方法がわからずに困っています。私も人に聞いて回っていますがわかりません。ラインとかで人に聞きたいことをまとめて私に送ってきたりしますが、文章にはびっしり細かいことまで書けるのに、いざ人に向かって話す段階になると、言葉になって出てきません。 (A男)
★福岡東部の集い 6月 22日 (日) 13 :3 0~16 : 00 ( コミセンわじろ ) 参加者3名 (女性 2 男性 1 )
〇 今年に入ってから頓に参加者が少なくなった感じです。勿論少ない乍らも話は進んでゆくのですが、やはり一抹の寂しさは拭えません。当事者を抱えている方々の集まり故、この状態が奈辺に起因しているのかという思いも過ぎりますが、会の展望への示唆と捉える事も出来そうです。〇 先ず素晴らしいのが、常連会員さんたちに対する心遣いです。他の会合ではこうはいかないのでは。会の成り立ちそのものが、自他共に思いやる事で始まっているのですから、顔が見えなかったら当然のことながら「心配」の二文字が会話の中に見え隠れしています。本日もそれを感じました。
〇 今日の大きな話題は、親がいきなりなくなった時、或いは介護施設に入るとか、急病で長期入院になった時、「どうすればいいか」を当事者にわかってもらっているか、ということでした。
子どもにその時の冷静なる対処法を理解させているか、就労だけを目的に置くのではなく、「生き永らえる」道を教えているだろうかということです。会員の皆さんは、この認識を持っておく必要があるということでした。 日常会話ではおこりにくい話題です。が、絶対必要な事だと思います。110番や119番、自治体の支援先のリストを提示するだけでは全く話になりません。親が身を以て伝える課題だという事を周知していきたいものです。
〇 どんな集まりも変貌の時を迎えます。大切な事はその変化の先に、未来が開ける事です。それは家族会そのものの課題であり、会員一人一人の意識であり、当事者の自立を促すものである事を期待するものです。穏やかな会話の中にもこの思いは共有されたのではないかと思いました。
今年も暑くて長い夏が予想されます。東部の方々はじめこれを読まれている全ての方の心と身体の充実を祈念しております。 ( H. K )
★福岡の集い 6月 26日 (木) 14 : 00~16 : 00 (あすみん) 参加者 19名 ( 男性3、 女性16 )
〇今回は〚親の終活と親亡き後の備え〛というテーマの講演会でした。〇会場にはここ数年お目にかからなかったお顔もあり、このテーマがいかに皆さんの気がかりな問題であるかがよくわかりました。今回の講師、福岡市社会福祉協議会は、今、国としても喫緊の課題である高齢者対策として、NHKTVにも出演されたと言うモデル事業であるということでした。全般には終活の話でしたが特に障害やひきこもりという特殊事情を汲んだ新しい事業のお話もありました。終活の必要性を思いながらなかなか手が付けられない私たちに、どのようにやっていけばいいかを具体的に整理してお話していただきました。会報の前半の記事も併せてお読みください。(F・Y))
(注)申し訳ありませんが、このホームページには会報の前半の記事は掲載していません。ご興味のある方は福岡「楠の会」だよりを御参照ください。
↑楠の会ホームページトップへ